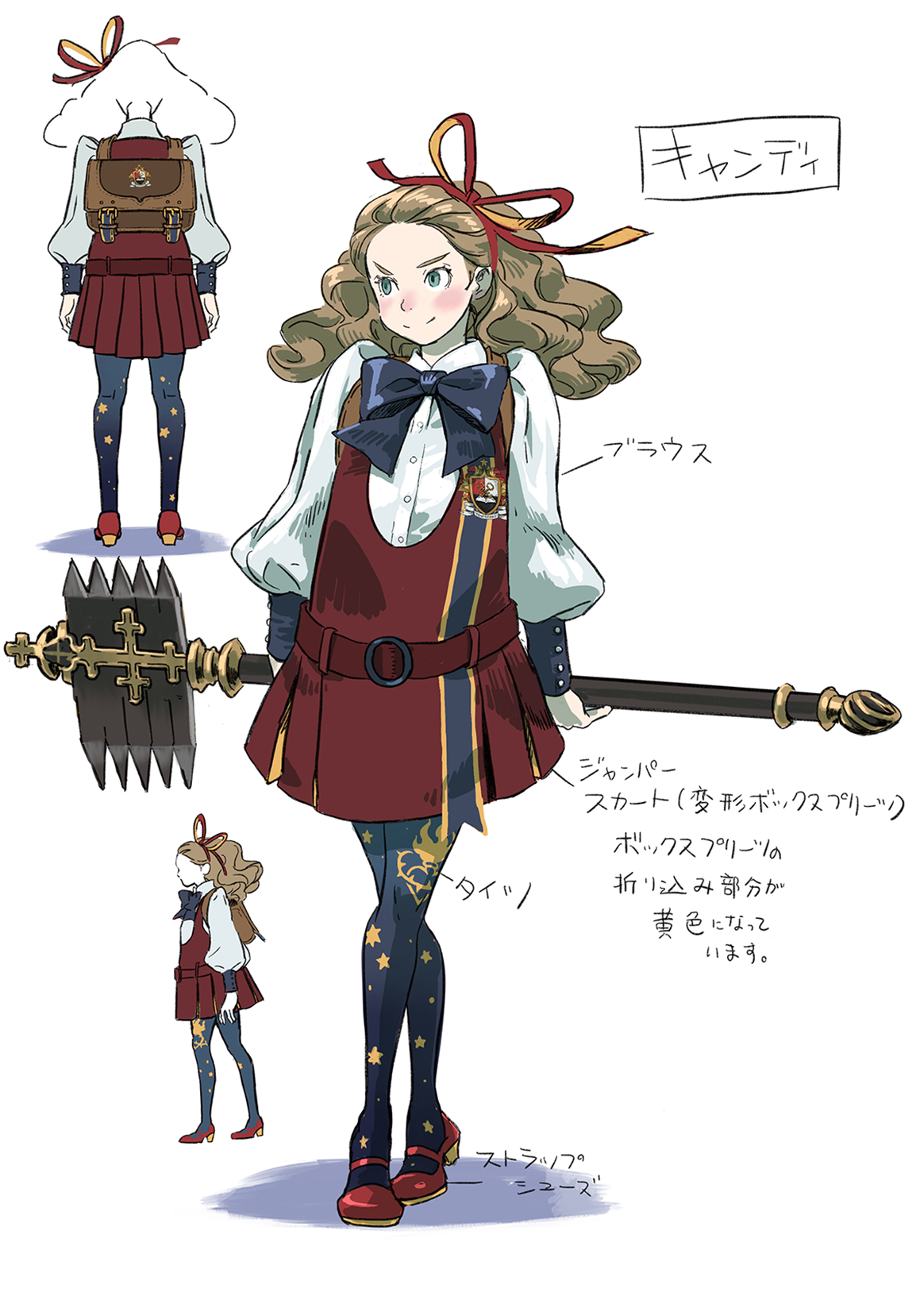22 9月 Penny Blood Side Stories #2
/*! elementor - v3.6.8 - 27-07-2022 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}THE DEVIL IN ME BLUES By Ari Lee 1青白い亡霊が闇を切り開いた。亡霊たちは深い森からうじゃうじゃと湧きだし、町を見下ろす丘の開墾地に群がった。茂みに潜むコオロギの声を聞き、時折、隣の者に話しかけながら、彼らは仕事をこなしていた。辺りの空気は風もなくしんとして、夜は上弦からふっくらと膨らみ始めた月に照らされていた。ほどなく、白い亡霊たちの下に、チラチラと緑に光る者たちが集まった。開墾地の中央で、白い影が違う長さの2本の木製ポールを十字架の形に縛っていた。彼らは十字架の周りにしゃがみこみ、灯油の強い臭気に少しむせながらも、そのひどい臭いを放つ油に浸された何枚もの麻袋で十字架を覆っていた。背の高い赤色の影が森から現れ、亡霊たちの働きぶりを称えながら開墾地の中央まで歩み出た。続いて4人の白き者が寄り集まり、寝かせてあった十字架を起こし始めた。赤い亡霊は十字架のそそり立つ姿を見て小さな畏敬のため息を漏らした。大きな変化の燃え盛る象徴であり、彼らが神の意志を全うする契りでもある十字架。神は天使を通じて彼らに語り、大いなる力を与え給うた。ついに彼らの時代がやってきたのだ。亡霊たちは木造の十字架の周りに大きな円を作り、それぞれの手に小さな木片を持って振りかざした。そして木片の切っ先につけた麻布に火をつけると、その火を1人ひとり隣の者の木片に送り、大きく燃え盛るリングを作った。炎は彼らの高く尖ったフードと、その真ん中に開いた、目玉を縁取る深い陰を照らしだした。亡霊たちは何度か円を描くように行進してから立ち止まり、木片を中央に鎮座する十字架へと投げつけた。投げられた木片の中には十字架に届かず、青々とした草や雑草を焼いたものもあったが、いくつかは十字架の足元にまで届き、数分後には大きな炎が上がり始めた。赤き者は誇らしげな微笑みで、燦々と輝くオレンジ色の炎が麻布を伝わり、闇を切り裂き聳えるのろしが出来上がっていくのを眺めた。白い影の数人が喜びの声をあげた。赤い影も大きく叫び、そして手をあげて静寂を命じた。「さぁ、兄弟たちよ」赤き者が深くかぶったフードの奥から呼びかけた。「黒人を狩りに行こう」2「あぁ、そして夜は哭いた~」薄暗い照明に照らされ、後ろに響くバンジョーのリズムに合わせて彼女は歌った。腕を伸ばし小刻みに身体をくねらせながら。白いクローシェ帽から唯一逃れた、太く黒々とカールした一房の髪が、汗で顔の横に張り付いていた。細い肩には黒いファーのストールがかかり、キラキラと輝く白いドレスに垂れていた。「探さないでと言っておくれ 私はもう二度と戻らない」その小さな地下室では、黒人の男女が肩を並べてステージを囲み、音楽を聴いていた。タバコの煙でかすむ部屋の天井はあまりにも低く、男性の中にはまっすぐ立てず、前かがみにならなければならない者もいた。ハーレムにはこういった地下の密売酒場が多かった。ロクサーヌ・アーシャンボーはこれまでに、そのすべてのステージに立ち、歌っていた。「心配しないでと言っておくれ だって私の中には悪魔がいるの」身体の動きを止めることなく、ロクサーヌは頭を振り、歌っていた。一瞬、焼ける肌と燃え上がる血の記憶が頭をよぎったが、彼女は目を閉じ、魂を込めた呟きですべてを追い払った。彼女の後ろでは、大きく禿げ上がった頭を汗まみれにしながら、ガスがバンジョーをかき鳴らしていた。「悪魔払いと親父にぶたれたけど もう親父はいないのよ」曲がクライマックスに入る瞬間、ロクサーヌはくるりと一回転をしてその場にいる知り合いと、これから知り合いになるであろう人々を見渡した。すると、帽子を膝に抱え、片手でジンのグラスを持ったハンサムな青年がカウンターの端に座っているのが目に留まった。その眼はロクサーヌにくぎ付けで、彼女も彼の見た目を気に入った。彼の眼は子犬のようで、その腕は壁を打ち抜く槌の如く屈強だった。「おぉ~ おぉ~ おぉ~ そして夜は哭いた~」最後の寂しげな響きとともにバンジョーがようやく静まり、地下室は拍手と喝采の渦となった。多くの観客がロクサーヌにコインやドル札を渡そうとしたが、彼女は笑いながら首を振ってカウンターの後ろにいるバーテンダーの方を指さした。「音楽を気に入ってくれたのは嬉しいけど、私たちここでぼろ儲けしようって言うんじゃあないの。感謝を示したいなら、皆さんシルベスター君のためにもう一杯飲んでくださらない?あのおっちゃんには子供が6人もいるのよ!」と、彼女はくすくす笑いながら言った。客らはこれにもう一度拍手を送り、帽子を頭の上で振り賛成の意を表した。間もなく、人々はバーカウンターに列を作った。ロクサーヌはその様子を微笑みながら見ていたが、いつの間にかまたカウンターの端に座っている、子犬のような目をした男を見ている自分に気がつき、彼の方へ少し近づいた。そして腰にぶら下げていた小さなポーチからタバコを取り出して口に咥えた。クスッと小さく笑い、一瞬、白い歯を見せて笑顔になった後、彼はマッチを取り出して彼女のタバコに火をつけた。「素敵な歌声ですね」ロクサーヌがタバコを吸いこむのを見つめながら彼は言った。「本当に素敵でした」「火をありがとう」彼女は返事をすると、最後に一瞬、暖かい笑顔を見せてから向きを変えゆっくりと歩き出した。「もうお帰りですか?」彼は呼び止めた。「出会ったばかりなのに!」「ロクサーヌは忙しいんだ!少なくともお前のような野良猫とおしゃべりするよりやることがあるんだろうよ」と別の男が笑いながら言った。ロクサーヌが地下室をゆっくりと歩く間、そこには笑いと喋り声が響いていた。一瞬、ロクサーヌの頭に、槌の腕の青年がデートに誘ってくる妄想がよぎった。きっと飲みながらたくさん笑い、お互いの笑顔が絶えない夜になるだろう。素敵な夜にならない理由はどこにもなかった。うまく行けば、きちんとした関係性にさえもなり得る。そして、夜が明けたら...